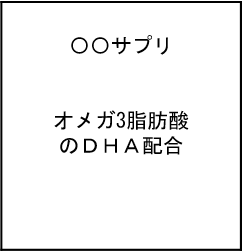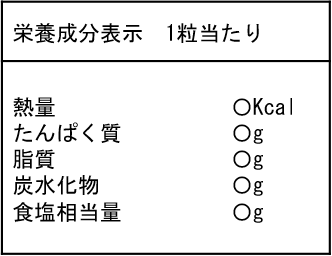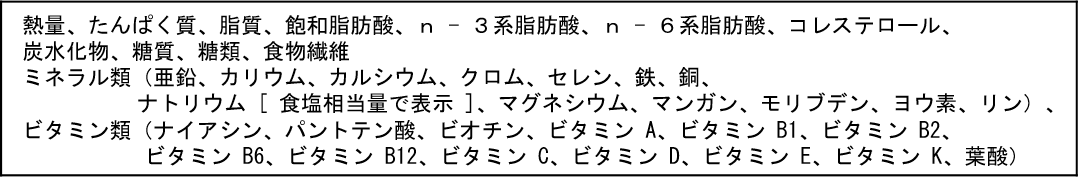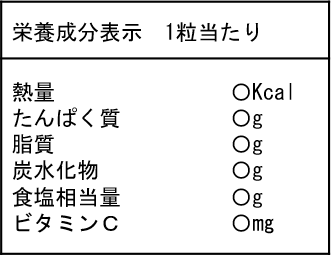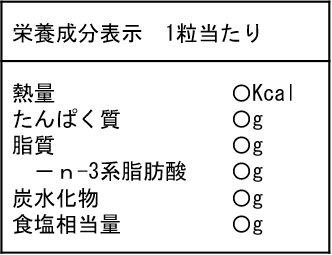A.コラーゲンドリンクALFEのサイト。冒頭に「美肌と
コラーゲン」の関係が述べられていて、下に降りて
行くと「Products」としてALFEが出て来ます。
これは都庁がNGとしている「記事風広告」に該当し、
NGではないのですか?
B.最近カルピス方式が影を潜め、リタゲ方式をあまり
見なくなりました。ALFEの例で、「美肌とコラー
ゲン」の記事にSEOでアクセスした人にリタゲを当て
て、そのリタゲからALFEの商品LPにリンクするという
手法はNGですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
A-1.たしかにALFEの建て付けはNGとされる「記事風
広告」の建て付けと似ています。
2.しかし、NGとされる「記事風広告」においては、
下の商品紹介の部分に「植物エキス〇〇〇配合」
と書かれており、上の成分記事とのつながりが鮮明
です。
対し、ALFEの場合は、Productsのところに「コラー
ゲン配合」とあるわけではないので、上のコラー
ゲン記事とのつながりは不鮮明です。
なので、こちらは必ずしもNGとは言えません。
B-1.カルピス方式がなぜ影を潜めたか?については、
テキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・
素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>」
をご覧下さい。
2.カルピス方式の例では、L92乳酸菌の成分効能
サイトに導くバナーが「アトピー」や「花粉症」
を訴求しており、とても強烈でした。
対し、ご質問の例だと、記事へのアクセスはSEO
で獲得するということで、さして強烈ではありま
せん。
なので、ご質問の例はかならずしもNGとは言え
ません。